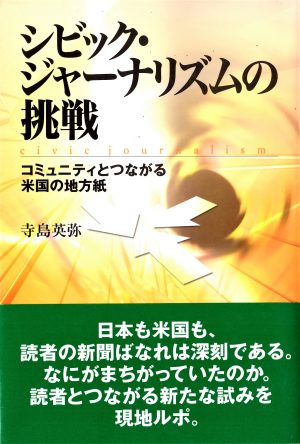シビック・ジャーナリズムの挑戦―コミュニティとつながる米国の地方紙
- 単行本(ソフトカバー): 256ページ
- 出版社: 日本評論社
- ISBN-10: 4535584125
- ISBN-13: 978-4535584129
- 発売日: 2005/5/20
- amazonでのご注文(kindle版あり)
はじめに
二〇〇二年八月から翌年三月まで、フルブライト研究員として米国のデューク大学(ノースカロライナ州ダーラム)に滞在した。本書は、そこで出会った「シビック・ジャーナリズム」あるいは 「パブリック・ジャーナリズム」について、日本の地方紙記者からみての報告である。二つの名称は、それぞれ命名者がいるが、同じ概念、価値、運動を指すものとして語られ、派閥などを意味するものではない。ただ、併記は少々わずらわしいので、本書では、筆者の耳に最初になじんだシビック・ジャーナリズムのほうを主に用い、取材した人ごとに語った名称を文中の「 」でそのまま記した。
新聞が読者とのあいだの距離を縮め、交わり、たがいにかかわりあい、ともにつくる「場」とな る――。シビック・ジャーナリズムは一言にすれば、従来の新聞のあり方を変えるアイデアであり、 一九九〇年代はじめ以来、全米の新聞の五分の一以上が実践しているという運動だ。記者歴が四半世紀をこえた筆者は、日本でそのことばを聞いたことすらなかった。日本と米国があらゆる分野でつながりを深めてきたなかで、新聞の世界は交流も情報もいまだに乏しい。両国の新聞文化に根ざすちがいはたしかにあるが、読者の新聞ばなれなど、重なる問題状況も多い。それを解決する手だ てとして米国の同僚たちが実践するシビック・ジャーナリズムを知り、地方紙記者である筆者なり の見方で紹介したくなった。
一九九〇年代からの長い不況は、広告、販売の両面で日本の新聞の経営環境を変えてきた(朝夕刊セット部数で一九九三~二〇〇三年に計約二〇〇万部減。日本新聞協会調べ)。それを象徴する傾向が、都市部住民の身近な地域のニュース源だった夕刊の低落だ。固い広告主でもあった地元ビジネス、読者の家族・家計への不況の影響や、新聞に情報を依存しない層が増えたことも要因とされる。職場や携帯電話でインターネットのニュースをチェックし、家ではテレビのニュース番組を見る、といったふうに生活習慣そのものが変わりつつある。
経営上の判断から夕刊を廃止する新聞も出ているが、筆者のいる仙台の河北新報は、その再生の方向を選んだ。いまなお発行一○万部をこえる夕刊を「都市生活者のメディア」と位置づけ、独立の夕刊編集部を設けて新しい紙面づくりと読者の掘り起こしを試み、全国の新聞社から注目されている。「どうすれば新しい読者をつかめるか?」の処方箋を、だれもが探しているからだ。夕刊の廃止にプラスの効果があった、という例もあまり聞かれない。それに代わる、読者への新しい提案をなかなか打ち出せないためかもしれない。
視点を変えて、そんな新聞の現在を読者はどうみているのか。新聞協会広告委員会の「二〇〇三年全国メディア接触・評価調査」は、市民三八七三人(複数回答)に、新聞とテレビ(民放とNHKは別)、インターネットなど六つのメディアの印象と評価を三〇項目についてたずねた。それによると、新聞は「情報源として欠かせない」「社会に対する影響力がある」「地域や社会のことがよくわかる」など、伝統的に評価の堅い半数の項目で優位だった。
一方で、「情報が正確」「情報内容が信頼できる」「わかりやすい」「中立・公正である」「専門的である」「プライバシーに配慮している」「社会的弱者に配慮している」などニュースの質にかかわる項目ではテレビ (NHK)が高い評価を得、「情報量が多い」「多種多様な情報を知ることができる」「時代を先取りしている」ではインターネットが優位になった。とくにインターネットは、ブロードバンドの常時接続サービスが普及したことで、テレビのゴールデンタイムと重なる午後九時前後の利用者が飛躍的に増えて日平均三○○万人に近づき、身近な情報源としての地位を高めている(『ブロードバンド環境下における視聴行動変化』日本広告主協会Web広告研究会)。 ,
それでは、読者の新聞ばなれは、他のメディアに優位を奪われての現象ともいえるのか。筆者は、 そうとは思わない。もっと大きな環境の変化が周りでおきているのではないか。一つの仮説は、役所の記者クラブや政党などに足場を置いた伝統的な取材だけでは、おそらく現実をすくいきれなく なってきたことである。
たとえば、こんな声はどこの現場でも聞かれるのではないか。「重要なことは役所でおきている、 と思いがちになり、だれに向けて書いているかという『読者』が具体的に浮かばなくなる」。そして、選挙で「無党派」と呼ばれる層について、「街や近所ですれちがっている人たちが、なんで選挙になると、無党派という、つかみどころのない存在になるのか」「おれたちの関心も、候補者の陣営関係者と同じく、どちらが勝つか、だった。その枠ではわからない人たちを『無党派』 と呼んで、わからないままにしてきたのではないか」
一言にすれば距離感か。もちろん日々の取材で、現場の記者はたくさんの人に会い、記事を書いている。地方紙ではとくに、取材相手イコール読者であることが多い。そうでなくても、新しい読者をつかむチャンスである。その貴重な出会いを「つながり」にしていくにはどうするか。無党派も新聞ばなれする人びとも、やはり距離感の遠さが理由であれば、近づけるための新しい方法論があるはずだ。取材者の側も、懸命に模索しているところである。
二つ目の仮説は、新聞がよって立つ「地域」が変わってきたことである。記事にもよく登場する地域ということばを、筆者は「地縁」「そこに住む住民を含めた地域」と同義か、と長らく思ってきた。いいかえれば「コミュニティ」。行政組織の末端である町内会も、政治家の後援会も、お祭りも、まちづくりも、趣味のサークルも、昔から地域が活動の単位であり、地元紙を支えてきた固 い読者層も取材対象も、地域のつながりのなかにあった。その基盤そのものが、急速に変わってきたのではないか。
たとえば仙台。一九八八年に政令指定都市となって、都心は再開発されてマンション群が立ち、 郊外には団地が広がり、新住民が全国から集まって「東北の大きな町」を百万都市に変えた。地域とコミュニティは同義ではなくなった。古い地縁は、日本中の都市部では分解したといってもよいのではないか。そのズレに、筆者も長らく気づいていなかった。たとえば、マンションは、何百、 何千人が住む一つひとつの「地域」であっても、隣人とのつながりさえ薄い。
米国で知ったのは、「コミュニティ」の新しい意味だ。シビック・ジャーナリズム関係の記事や文献では、このことばがよく出る。筆者はその都度、「地域」と頭で変換したのだが、ギャップを感じた。あるとき、調査で訪ねた先の地方紙の人に問うと、「地理的な『地域』よりも、むしろ人の集まりそのもの」との答えが返った。人種やジェンダー、世代、関心や趣味、仕事や市民活動、 信仰、マイノリティなど、さまざまな関係の「場」でつながる人の集まりがコミュニティなのだそうだ。単に人が住まう町内のような地域は“Neighborhood”(近隣)であり、最近のマンションなどもこれにあたる。
なぜ、「コミュニティ」がキーワードなのか。その米国の同僚はこう説明してくれた。家族の解体、移民や貧困層の増加……。日本に先駆けて複雑に、急速に地域社会が変化した米国では一九八○年代、不況とも重なって深刻な読者の新聞ばなれがおきた。その変化を新聞の側が読みとれず、 伝統的な地域のきずなが分解するのに代わって、多様になったコミュニティや個人との新しい接点をつくれなくなった。「読者が新聞をはなれたのでなく、いつの間にか新聞が読者からはなれていた」と評した。現在の日本の新聞をめぐる状況と似ているのではないか、というのが、そのとき、 筆者が得た問題意識だった。そうした目でわれわれの周囲をながめ直してみれば、地域は分解し、 いくつもの「場」に変わったのがみえる。
衝撃的な少年犯罪が「一七歳」から「一四歳」、そして小学生へとすそ野を広げ、大人からは 「わからなくなった」子どもの世界。離婚や非婚が増え、個々の生き方の選択とともに一つひとつ形も変わってきた家族。無数の小宇宙のようにネット社会を広げる若者。四〇〇万人といわれるフリーター。世間の声を映してきた新聞の社会面を素通りし、事件の当事者に殺到する電子メール。 不況下で職や家も失った人びと。年金問題が露わにした、異世代間で対立する言い分と不満。自立への自己選択と環境づくりの広がりを求める、病気や障害のある人びと。企業の犯罪や不正行為を告発する消費者たち。地震などの災害現場に集い、全国に人脈を張るボランティア。退職者や主婦らが広げるNPO(民間非営利団体)などの市民活動。マイノリティとしての孤立や偏見と闘う在日外国人……。
机に座していては接点をもちえない「場」は、一つの地域のなかにも数かぎりなくある。記者たちが新しい目をもって地域を歩き、新しい時代のテクノロジーを用い、多様なコミュニティへの入り口を見つける。それぞれの「場」の人びとが語る事実に耳を傾け、そこにある問題を掘り起こし、 読者に議論をおこし、支援や解決にかかわっていく――。一言でいえば、それがシビック・ジャーナリズムの特徴なのだ。米国の地方紙の同僚たちが苦境のなかから見出した、新聞が読者とのつながりを再生するための提案である。
· 取材者の側が構成し、伝えるストーリーとは別に、語り手自身がつむぎ出す事実を Narrative (ナラティブ)という。一つひとつのコミュニティの発するナラティブに誠実であることを、シビック・ジャーナリズムは求める。それを知ってから、筆者自身の苦い経験を思い出した。
数年前、子どもの病気をテーマに、親の体験を語り合うフォーラムにかかわった。そこで、障害のある赤ちゃんをもつご夫婦を「不幸にも……」と紹介し、また、重度の障害のある子を育てる別の母親の長い訴えを、途中で打ち切らせてしまった。「家族には家族の悩みも喜びもある。障害児をもつことを不幸と思わせる社会のありようこそが不幸」と後に叱責をいただいた。場を求めて参加しながら、語り尽くせなかった母親の心情を思うとき、そこで何も感じなかった事実に今なお痛みがある。
たとえば、障害観そのものがこう変わってきている。「障害は、社会のマイノリティの問題でも、 身体の障害によって表されるものでもない。それは、よりよい生活や活動を可能にする支援のない 環境や、人と人の関係に存在する」(WHO「国際障害分類』二〇〇一年、より要約)。まさに人と人の関係をつなぐのを拒む行為ですらあった。
筆者はまたあるとき、再開発をめぐって「先祖以来の家と暮らしを奪われる」と訴える人たちを、 役所サイドの表現で「反対派」と書いてしまったこともある。いずれも、自分が頭に描いたストーリーの側にとどまり、それぞれのコミュニティの生きたナラティブに耳を傾けることができなかっ た実例である。今、そうした声たちの受け皿となっているのが、インターネットの世界なのかもしれない。
シビック・ジャーナリズムとは何か。二つの国の新聞文化のちがいも学びながら、現場の新聞づくり、読者との新しい関係づくりにどう生かすことができるか。米国の地方紙のさまざまな模索と努力の事例を、筆者の体験を交えて報告しながら、読者といっしょに考えていきたい。