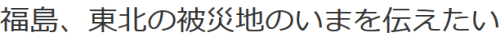「事実」が閉塞に風穴を開ける~授業で語られたジャニーズ、強制不妊手術の取材
週刊誌報道の取材現場から語った白川さん

4年目になるマスコミュニケーション論の授業は、タイムリーな話題を~と(やりくりの上)、ゲストを招いて現場のお話をしてもらう。2回目(10月7日)は白川遼太郎さん(一昨年に続き2度目)。現在、小学館の週刊ポスト、女性セブンの編集者、前職は週刊文春の記者でいらっしゃった。テーマは、〈「ジャニーズ」「フジテレビ」問題とメディア~マスコミュニケーションは働いたか、どうあるべきだったか?〉。
4年前に文春がスクープし、裁判で性加害問題を事実認定された芸能界のドンが、追随報道の追及もなく、とりわけテレビ業界を支配し続けた。なぜだったか? そして、まるで黒船来航のようなBBCの告発番組を機に、公然たる秘密の情報のダムは決壊し、当時の社長謝罪会見、第三者委の全貌公開、“帝国消滅”に至った。しかし残った種火は昨年暮れ、白川さんがいる週刊ポストの中居正広さん性加害疑惑報道となって再燃。大テレビ企業を根っこから揺るがせた。なぜ、事実を報じるマスメディアが、ジャニーズ問題から変わらず横並びで、「報じないメディア」になっていたか? 白川さんはさらに、視聴率・ビジネス・商売と、報道の現場の間に線引きがない古い体質を、取材の内側から語ってくれた(筆者は35年前の米国で、営業の人間が編集局に立ち入れぬ「倫理綱領」を知った)。
隠されてきた問題を掘り起こした加地さん

「一人の声の発信が社会を変える」がテーマの5回(同28日)は、戦前から戦後、障害のある人々が全国で不妊手術を強制させられた問題を、神奈川新聞記者の加地沙耶香さんに聴いた。旧優生保護法による不妊手術の犠牲になったのは約16500人に上り(旧厚労省の統計)、それに当然の違憲判決を最高裁が下したのは昨年7月。ナチスの断種法ともルールを同じくする人間差別の法律と手術が、なぜ公に知られることなく延々続いたのか(同法廃止は96年)。そのきっかけをつくったのが加地さん。河北新報の新人記者だった2017年、偶然の取材で仙台で出会った被害者の女性の話に揺さぶられ、たった一人で声を上げようとしながら無視されていた彼女の声を伝えたい、思い立った。しかし、職場には職場の仕事が厳とあり~新人でもあり~、思いを果たせない加地さんは退職。大学の恩師や先輩らがつくったウェブニュースの取材者となり、加地さんはバイト生活をしながら、全国にまたがる事件を掘り起こした。各県で地元の医療・福祉・教育・経済の団体、マスコミなどが社会運動として事実も「開示請求や取材に明け暮れた日々」から明かしていった。
一人の当事者の声と事実が社会に風穴を開ける
お二人の授業で語られたのは、たった一人の当事者の「事実」が社会に風穴を開け、その声が同じ境遇の人々の声を呼び起こし、衝撃力のあるニュースとなり、それまでの社会を(世界をも)変えてしまうことだ。言葉を換えれば、報道に携わる者は、社会に発言する権利を奪われた当事者の声を人から人、地域、社会につなぎ、閉塞した状況に風穴を開ける伝え手、問題解決へのつなぎ手の役目を持つ。常に新鮮な情報やメッセージが、水や空気のように常に流れ循環してこそ、あらゆる人が差別、疎外されることなく考え、発言し、活発な議論、正しい判断、決定をできる。メディアの本義とは、にあって人と人をつなぐもの。情報が歪められ混乱する現在だからこそ、それを担う役目は大きいと思う。
白川さんは編集で携わるもう一誌「女性セブン」で8月、フジテレビ問題で仮名が上がった、福山雅治さんのインタビューを単独で報じ、ありのままの言葉を伝えた。「ライバル誌もいた中、信頼してもらえる関係を築けたから、語ってもらえた」と話した。受講生からも、「信頼をつくれることがメディア、取材者の条件だと知った」という意見が、授業後の感想カードに書かれた。信頼とは、中間にいるメディアのもう一方の存在、読者・視聴者である市民との間にもなくてはなるまい。また、被害を訴えながら孤立した女性のもとに真摯に通い続けた加地さんには、「バイト生活をしても取材を続けられたことに驚いた」、「日常にある小さな問題にも目を向け、声を上げたい」という感想が寄せられた。

ありがたいのは人の縁
ありがたいのは人の縁だ。白川さんは仙台の人で、メディア研究のゼミにいらっしゃった大学時代に筆者が震災取材の話をさせてもらったが出会い。加地さんは大学生のころ、同窓の筆者も関わった新しいメディアづくりの活動に参加されていた。古巣の新聞社時代、彼女の悩みを聴きながら力になれず、悔いが筆者にあった。お二人とも授業で語ってくれたのは2回目。新しい縁が生まれたことが本当にうれしく、来年も来ていただこう。 (寺島英弥)