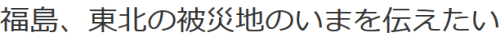学生たちと新聞を題材に、文章トレーニングで向き合っています
新人教育のライブ感を思い重ねて…
尚絅学院大で今年から授業の傍ら「学習サポートセンター」の講師を引き受け、リポートを書ける文章力や文章表現のトレーニングのクラスで学生たちと向き合っている。
教室では、お題を出した原稿をPCでもらってプロジェクターで壁に映し、その場で手直しを赤字、理由や助言を青字で添え、良い文章や言葉選び、着眼をほめ、対話していく。新聞の世界で身についた文章の約束ごと、流儀、作法がベースになっているが、その良い点は、書き手の我流でなく、一読で分かる「読者視点」を働かせながら書く習慣を身に付けさせるところか。
そのライブ感が❝OJT❞(現場教育)のだいご味だった。新人さんや若い後輩の原稿を隣に座らせながら直し、その理由に答えるやり取り(直しの訳を抗議口調で問われながら)から新聞原稿は仕上がる。その数え切れぬ経験があるから、学生さんの文章を読むのは何人でも苦にならず、新鮮な言葉や発想を見つければ楽しい。
記事を読んでのモヤモヤ感覚を言葉に

最近気になったニュースを、それぞれのお題にしてきた。今週から河北新報朝刊を地元販売店から、授業日ごとに人数分届けてもらい、教室ですみずみまで読んでもらう。ネットのニュースは「.」の関心でしかないが、新聞は地域からこの国、世界で起きた一日のニュースのパッケージ。受講生たちに新聞読者はいないが、紙面をめくっている間、さまざまな出来事への関心が続き、その中で何かしら「気になる」情報がある。気になった理由が何かしら読み手にあるのであり、そのモヤモヤを言葉にしてもらうのが、授業の前半だ。そこから感想でなく「意見」を文章にして書いてもらう。
あるニュースが気になるもやもやには、自分の中に関心の理由があり、あるいは何らかの当事者である体験があったり、「それは自分にとって何だろう、どういう意味があるのだろう」と考える瞬間を、ニュースが待っていたともいえる。その出来事があった社会や地域、問題と自分とのつなぎ手がニュースであるとも。
頭の中の【考える畑】の肥やしにニュースを
ある授業で、白石市であったアーケードの夜のイルミネーションの記事を選んだ学生がおり、「なんとなく…」という彼にその理由を問うていくと、自分の郷里の町の若者がいない夜の寂しさが胸に浮かんだ語った。それを結び付け考えさせる力が、記事の取材記者の意図を超えて、ニュースにはあるのだと思う。
「今の学生は書けない、書く力がない」と聞くが、教室で学と生さんには「頭の中には『考え』を生み育てる畑があって、ニュースでも本でも出会いでも、新しい情報・体験という肥しを入れないと、何の『意見』も生まれないよ」と話す。そんな多彩な肥しに新聞はなると思う。
この夏、校條諭さんが宮城県丸森町で催した「熱中小学校」で、全国の新聞から関心ある見出しを集めた「自分だけの新聞」を大勢の人がつくる作業に触れ、その可能性を私自身も見直せた。教材に使わない手はない。 (寺島英弥)