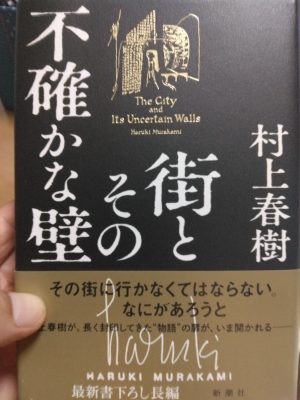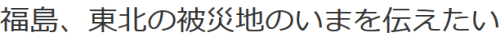『街とその不確かな壁』を読んで~カフカのような迷路をたどる先には…
村上春樹の「街とその不確かな壁」(2023)をお好きな方はいらっしゃるだろうか。カフカみたいな迷路のような上下巻を読み、分からない細部の意味を考え直そうと2回目を読み、また頭の中で寝かせて、やがて忘れて、またふっと降りてきたものがある。
眠るたびに観る夢は、実は、自分のいるもう一つの世界のように感じたことはないだろうか。ばかばかしい話かもしれないが、晩ごとに、同じ夢の続きに自分が生きているように…。
この小説も、同じ著者の「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」(1985)などのように二つの異世界を行き来する。一本一本の明晰な文章をたどるうちに迷宮に導かれる過去の愛読書と印象が異なるのは、「街とー」のもう一つの世界、すなわち街が、夢と同じ素材で編まれ、それが死者たちの場所のように思えること。主人公が少年時代から愛した女性の失踪が、実は死であり、それを受け入れられぬ彼が創り出した街なのではないか~彼女を永遠に死なせずに住まわせる街。
だから、そこには時間がなく、住民には影がなく、死者たちの果たせぬ夢を読む仕事があり。外界と隔てる壁が絶えず生きているように動くのは、主人公の意識が生み出した境界であるがゆえ。だから、二つの世界を行き来する主人公が、現世で死者の幽霊を見、対話ができるのも不思議はない。筆者の少年時代からの大事な友人が亡くなり、夢で会ったような個人的な出来事も、そんな気づきにつながった。
やがて現実の生を選び、愛する女性の住む街を去る主人公の彷徨の痛切さは、著者の作では「ノルウェイの森」(1987)に近いと思う。その小説も発売当時は、あまりの人気ゆえの軽さのような違和感を覚えて遠ざかったが、後に観た松山ケンイチ主演の映画がきっかけで違う風に読み直せた。ここまで長~い極❝私的❞つぶやきですみません…。(5月21日)