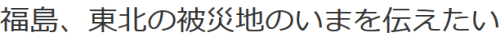九州への旅で出合った高千穂町の棚田と、巨大半導体工場に優良農地を差し出す熊本の現実に、日本の農業の危機を考えました
寒の戻りのさなか、初めて訪ねた九州は、東北に劣らず山が深かった。宮崎の高千穂町に差し掛かった折、バスから目を見張ったのは見事な棚田の連なりだった。小盆地の周りの山肌に見渡す限りに。これほど美しく田を保ち、不便さも厭わず、過疎と思われる町の農家は営々と耕してきたのだ。
旅の途中、久々に声を聴いた熊本の元地元紙の旧友が対極の現実を語った。熊本の小さな町に降ってわいたように進出した台湾の巨大半導体工場。空前の地域開発ブームのニュースが遠くに伝わったが、どうも事情は違うようだ。広大な立地先は県内でも優良なコメ農地だった。第二、第三工場へも農地の❝差し出し❞は続き、熊本の平野を潤す阿蘇の地下水大量くみ上げへの懸念が地元メディアで報じられる。
先日の中国・Deepseek登場で動揺したIT市場のように、一夜で技術、価値が陳腐化する世界と、貴重で豊かな農地を交換することのリスク、もう考え直さねばならぬのでは。異常気象のせいなどではなく、農水省の失政が招いた、先の見えないコメ不足。数年来、東北のサクランボやリンゴの農家廃業を取材し、「農地とは文化財」との思いを強めた。
目先の備蓄米放出のごまかしより、高齢化し先細りする農家の担い手を若い世代に引き継げる、「文化財」たる価値を高める方策こそが緊急だろう。各地からボランティアも集うという高千穂町の営々と受け継がれる棚田にも学びたい。