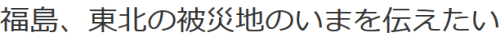被災地・閖上の取材5年目、受講生は「3.11」へ記事執筆に挑む
閖上取材に始まった授業は大詰めに


尚絅学院大の授業と地元名取市の被災地、閖上(ゆりあげ)との縁は5年目。毎年の受講生が、14年前の震災で何が起きたか、取材するとは何かーを学び閖上の現地を取材し、住民の皆さんの体験をインタビューで語ってもらい、それぞれの視点、問題意識で「次の3月11日」への記事執筆に挑む。「実践講座 当事者とつながる学びとスキル」と銘打つ授業は今年、目標の記事完成まで残り5回になった。
閖上と尚絅学院大の縁は深い。仮設住宅の時期から学生、教職員が支援と交流を続ける。授業では、長く交流に携わる職員の佐々木未央さん、学生ボランティア「TASKI」初代OG斎美紀さんが歩みと絆を伝えた。閖上の自治会長、長沼俊幸さんは10月26日の閖上取材の後も2度、教室に足を運んでくださり受講生たちと質疑を重ねた。現地で聴き足りなかったことを尋ね、もやもやとした問題意識から自分だけのテーマ案をプレゼンし、助言をいただいた。
自治会長が語った「終わらぬ震災」


長沼さんは、夫婦で屋根の上で津波に流されて助かった後、衝立もない避難所でのストレスフルな毎日、仮設住宅では閖上の仲間と助け合い6年の共同生活に耐えた。しかし、古里が流された跡に街を再建する市の方針に、悲痛な津波体験から内陸移転を希望した多くの住民が心離れ、「どこでもよいから仲間とまた一緒に暮らす。そんな、私の夢見た“復興”は消えた」と長沼さん。自身は新しい街に戻って自治会長に推され、新旧住民の融合に奮闘して14年。心には喪失の寂しさが膨らんでゆくという。「復興って何か。その意味を、閖上を訪れるいろんな人に尋ねるが、誰一人答えられない」。そんな言葉に受講生は、終わらぬ震災という大きなテーマをもらった。 あの日と今をつなぐ体験と思いは、閖上取材の折の集会所のインタビューで住民の方々も、それぞれの語りで受講生に伝えてくれた。
授業を助けてくれた新聞の戦友たち
授業を助けてくれたのが、古巣の河北新報で一緒に仕事をした戦友たちだ。編集部長の大泉大介さんは多忙な仕事を縫って、初回の「インタビューの意味と方法」の授業に来てくださり、筆者との模擬インタビューで、いかに相手との壁を越えてつながれるか、細やかな心配りと質問でいかに語ってもらうかを伝授してくれた。
東北から雲南、ネパールまで長い取材行の相棒だった写真部長・門田勲さんも、忙しい中、今年も教室に来てくださり、「人に伝える写真をどう撮るか」「人の心にどう伝えるか」を、自身の震災取材などの貴重な写真から解説。実際に受講生たちを教室の外に出してスマホで写真を撮らせ、一人一人に丁寧に講評してくれた。


いよいよ「記事を書く」最終ステージ
大泉さんはそれから宮城県知事選の取材指揮を執り、門田さんも同様で、渦中の苦心を紙面で知るにつけ恐縮し、元同僚たちの気持ちのありがたさをかみしめた。 こうして手づくりする授業も、いよいよ「記事を執筆する」という最終ステージ。新聞の“現場40年”の書き屋であった筆者も、昔、新人や後輩の記者さんたちと向き合ったように、経験の知恵を惜しみなく伝えたい。