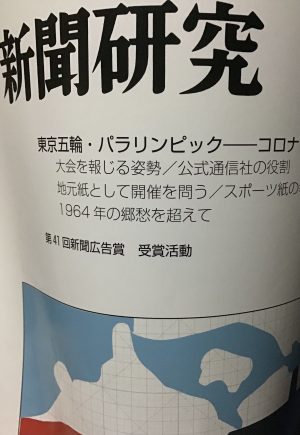「新聞研究」10月号に、論考「被災地が見た復興五輪の虚構」を書きました。
『新聞研究』(日本新聞協会)10月号は、コロナ禍の下の東京五輪がどう報じられたか?ーがテーマです。全国紙、通信社、東京紙、スポーツ紙、地方開催地の地元紙の運動部長、統括キャップらが執筆し、私はその現場から離れた東北の大震災、原発事故の被災地からどう見えたか?を書きました。
*一般客が生で見られないからこそ詳報する必要があった、不自由な生活を強いられる人々に質の高いエンタテイメントを提供したー。
*今は非常時、読者の命や暮らしに関わるコロナ関連の記事がより重要なのは自明の理だった。コロナに苦しみ、不安に思う読者の気持ちに添わない新聞作りはありえなかったー。
このように対称的な主張の社もあれば、淡々と取材態勢の記録のみ綴った国内公式通信社、それまでのワイドショー的紙面作りは果たして報道かと模索を続けたスポーツ紙、「我々は不要不急のメディアか」との揺らぎから五輪報道に再生を掛けた別のスポーツ紙など、内情はそれぞれ違いました。
ただ、「アンダーコントロール」なる元首相の虚言に始まった五輪について、「私たちには遠いどこかの世界の出来事」「もともと『復興五輪』なんてなかった」と冷めた被災地の声を報告した私には、どこか、ひと夏のパラレルワールド(二つの平行世界)のような読後感が残りました。いや、コロナと五輪の間で迷走した政治を加えれば、三つの交わらぬ現実があった夏か。それらの分断を一つにつなぐ努力は本来、五輪の興奮を追う前にマスメディアの役目であったのではないか、とも思われました。