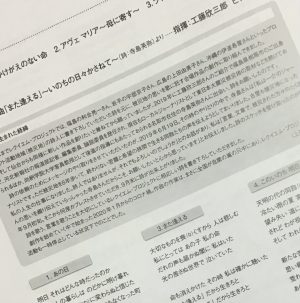被災地の詩に寄り添うレクイエム~上田益さんの音楽〈8月28日、レクイエム・プロジェクト仙台の演奏会より〉
「レクイエム・プロジェクト仙台」の演奏会が8月28日、仙台市の青年文化センターで催され、筆者も、地元や各地から集った約80人の合唱団に交じってステージで歌った。https://www.youtube.com/watch?v=u2aV-8bp2_s
仙台での演奏会は東日本大震災から3年目から始まり、この度が10回目。仙台だけでなく、全国の災害や戦災のあった土地の人々から合唱団を募り、地元の詩人と協働でオリジナルのレクイエムを作って、上演してきたのが主宰者の作曲家・上田益(すすむ)さん(65)。レクイエム・プロジェクトは、発祥地の神戸から東京、広島、長崎など現在7カ所に根付き、それぞれの演奏会を続けている。「詩に寄り添う、祈りと希望のレクイエム」。合唱の内側から上田さんの音楽に触れた筆者の思いだ。仙台の演奏会から感じたままを綴ってみたい。
◇
演奏会の冒頭を飾ったのは、広島で幼少時に被爆体験のある詩人、上田由美子さん作詩の『生きとし、生けるものへ』から、『野辺に』。広島や原爆につながる言葉はなく、ただ、<野辺に咲くりんどうの花>と歌い始める。
「私たちに伝えられるのは、目の前の小さな事実。その後ろに、隠れた大きな事実がある」。メディアリテラシーの授業で学生さんらに真っ先に学んでもらうセオリーは、詩の解釈にも応用できると思う。<野辺>という言葉で浮かんだのは、廃墟となった街のあちこちで煙が上がったという犠牲者たちの野辺の焼き場。そんな痛ましい死に満ちた野辺に一輪咲いた、鮮やかに青いリンドウを連想した。リンドウは北の花のイメージがあるが、調べると広く九州まで咲くという。
筆者の記憶にある花は、被災から十日ほどして訪ねた陸前高田で、津波が残した砂の下から咲いたスイセン。そのまぶしい黄色は、廃墟となった町に生まれた「生」の色だった。
詩人さんにとってリンドウは、そんな記憶の花なのだうか。<より添う露の光が、暗闇の中の花を照らす>と歌は続く。死の街と化した暗闇のような風景に咲いたリンドウに、露が宿ったという。筆者はまた「水ヲクダサイ」と口々に言い残して亡くなった犠牲者のことを思い起こす。わずか露の一滴でも、それは命の水。真っ暗な死の世界にあって、露を宿したリンドウは、命の再生の象徴であろう。そして、<地の下では巡りくる春にそなえて うごめくものを探りながら 命の糸の繕いが始まる>と歌は続く。
途切れたと思われた命の糸が一滴の露を得て、春がまた巡ってくることを思い出し、新たな生への繕いを始める。人もまた―。そんな光景が浮かんだ。暗闇のはかない花から始まる詩は、まばゆい光を呼ぶ。<命あるものはすべて等しく 自然の恵みが降りそそぐ>
上田益さんの音楽は、悲痛な響きの<野辺に咲くリンドウの花>から始まり、<光>の言葉で文字通り、まばゆい輝きを発する。そして、<誰にも気づかれずそっと咲く リンドウの花にも露がより添う>で合唱は確信のような強さを帯びてゆき、歌い手たちそれぞれが一輪のリンドウになったように、その思いを天に届けるかのような希望へと達する。
◇
筆者の友人でもある久慈市の詩人、宇部京子さんが作詩した『三陸鉄道が行く』という曲集も、地元久慈、野田村などの人々と上田さんが育ててきた「レクイエム・プロジェクト北いわて」が歌い継ぐオリジナルの作品だ。仙台の演奏会ではその抜粋が披露され、歌っていて心に染みたのが代表曲『とうさんの海』だった。
あの日の大津波の後、「海をもう見たくない、そばに住みたくない」と古里を離れた家族も多いと聞いた。『とうさんの海』の詩の主人公は、〈うれしいとき かなしいとき まよったとき つかれたとき〉にも、〈とうさんの海に会いにゆく〉。
<とうさん>について詳しくは書かれていない。想像するに、三陸の海を仕事場にしていた人だろうか。そして、主人公が大好きな父だった。あの日から時が経ち主人公は成長し、<とうさんとおなじ歩幅ですなはまを歩く><とうさんとおなじ目線で水平線をみる>ようになった。<かいがらをひろう>背中も、<はまなすをたおる>手つきも。そして、とうさんが愛した海だった。海が、とうさんを奪った恐ろしいものであるという思いを越えて、<とうさんの海は わたしのふるさと>そのものなのになった。
この詩に付けた上田さんの曲は、主人公の巡らす<とうさんの海>への日々の思い、詩の底に秘められた心の痛みにも寄り添って、限りなく柔らかく優しい。歌い手の心も自然に一つになる。曲の最後、<ザッポーン ザッポーン ザッラーン ザッラーン>という浜辺の浪の音が繰り返されるが、それさえ子守唄のように安らかで、被災地の数え切れぬ<とうさん>へのレクイエムになり、大切な人との思い出と共に生きる者への終わりなき癒しとなる。
◇
最後のステージは、筆者が上田さんから作詩を委嘱さた『また逢える~いのちの日々かさねて~』だった(昨年9月、多賀城市文化センターでのレクイエム・プロジェクト仙台の演奏会で初演)。詩人でなく取材者である筆者が被災地(相馬、陸前高田、石巻、飯舘村)で立ち会い、聴き取った当事者たちの思いと言葉が4編の合唱組曲になった。
当日演奏された抜粋の中で、レクイエムとなるのは3曲目の『また逢える』。津波でわが子を奪われた母親が、生きる望みと力を失い、自死さえ思い立った刹那、枕経に訪れた僧侶から聴かされた一言をめぐる、死と生の物語である。
沈痛な序奏から<だれの声も届かぬ闇に 私はいた><光のささぬ世界で泣いていた>と歌う主人公は、激しい心の奔流の中で一つの言葉を不意に耳にし、死と生の境で立ち止まる。ピアノの伴奏もそんな真っ暗な死の渕を描くように、あの津波のように荒れ狂う。
<命も消えかけたその時 私は確かに聴いた><「また逢える」 だから生きろと>
言葉を投げた側も主人公と必死で向き合ったろう、命懸けで呼び戻したのであろう。
<「いつか逢える」 だから生きろと><精いっぱいの命を生き その先であの子は待っていると><だから生きろと>。生と死の境でのドラマに、合唱は幾重にも呼び戻しの声を繰り返す。バッハの激しいフーガのように、共に母親の命を救おうとするかのように。
その激流がやがて鎮まると、真っ暗だった死の世界の縁に、にわかに、かすかに、ピアノの柔らかなアルペジオとともに光が差し込む。閉ざされていた主人公の心にも。そして誰の声なのか、<哀しみなさい 泣きなさい>と、最高の癒しのコラールが流れてくる。<哀しみのなか あの子は生きる>と。その霊感のような言葉はいつしか主人公のものになり、なぜならば<哀しみは私の愛 あの子の愛>なのだから、という目覚めのような心境に至る。
「いつまでも泣かないで、悲しまないで」と心配する周囲から掛けられたであろう虚ろな声はもう聞こえない。主人公の心に差し込んだ光も、荒れ果てた被災地の風景を照らし出す陽光ではない。彼女に見えるものは、<あの子>が導いてくれる一条の光なのだ。
上田さんの書いた合唱も、わが子との再会を信じ、<光の先のあの子に導かれ 残されたこの生(いのち)をたどる>と心に決めた主人公に、この上ない慈しみの宿るアダージョで寄り添う。<また逢える いつか逢える>という思いは、もはや母親の生ある限り、生涯最期の日まで変わらぬことだろう。それは喜びなのだから。合唱も、<魂となって逢える日まで>への深い静かな祈りとなる。