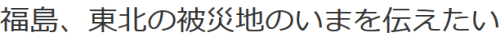【つぶやけない、ああでもない・こうでもない~の私】をつぶやきました…
書くと、長くなってしまう。どんどん長くなる。何か、その瞬間に浮かんだ思いや感情、ひらめいたことをだれかに伝えたいのだが、すぐにつぶやけず、いや、こういう面もあるな、これは口に出すには早いな、もう少し考えよう、と頭の中でぐずぐずしているうちに日がたち、ひらめいた言葉は長く長くなり、そのうちに新しいことが起こったり、事態が進展したり、別なことを考えたりして、タイミングを逃してしまう。俳句のようだった思い付きは、長いコラムでしか表せなくなる。それが自分の常で、フェイスブックの投稿が3週間、ひと月とご無沙汰になるのも、そんな性癖からだ。
記者時代は、文量として一番短い夕刊コラムを3年も持たされたが、それはほぼストック(書き溜め原稿)なしでやった。「風邪で休んだら、どうする?」と上司から言われたが、そんなSOSの事態は1回だけで、その朝のひらめき勝負で乗り切った。それは〆切があったゆえで、問答無用に自分を追い込める、というストレスフルな不健康な環境の中毒体質?になっていたゆえだろう。
新聞の原稿は現役時代で長くても1000~1200文字で、新聞の文字が大きくなるにつれて「短く書け」が至上命令になった。一方で、震災が起きてから日常にブログを書くようになり、五感で現場のありのままを盛り込めば8000~1万文字超えもふつうの、ああでもないこうでもない~が当たり前の感覚になり、今に至る。
この「無制限1本」のウェブ感覚を知ってしまった新聞記者は珍しかったと思う。新聞社内では「寺島さん、長いよ」と後輩のデスクに注文を付けられては、削って削って短くした。
ふとぼやくはずだったこの投稿も、いつの間にか長くなっている。ただ、長大に見える記事も、因数分解すれば短歌や俳句にもなり、どちらも同じ、というのが文章の不思議だ。
いま、3月11日に向けた記事の取材をし、構想し、書き始めているが、一言で伝えられぬ現実ばかりがあり、それを考えていると、つぶやきの種はまたいつの間にか、「ああでもないこうでもない」の大渦にのみこまれてしまう(それは大学の授業を考えたり本を書いたりするのに役立つけれど)。
フェイスブックに、つぶやきを書けない自分をつぶやくはずが、気が付くとまたまた長くなってしまっている。遥かな昔から「はっきりしなさいよ!」と言われた自分も変わっていないな、と気が付く。ともかく今年はつぶやいてみよう。