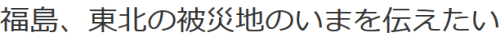校條諭さんからお誘い~「熱中小学校丸森復興分校」のワークショップに参加しました!
敬愛する校條諭さんからのお誘いに心から感謝。丸森でのすばらしい授業、そこに集う仲間との出会い、これからもぜひ参加したい素敵な場でした。自分の原点に帰って考える機会をありがとうございます!(7月28日)
◇
寺島英弥(Hideya Terashima)さんとの出会い
熱中小学校丸森復興分校(熱中丸森)で、ワークショップ「まわしよみ新聞」と講義を担当することになって、そうだ寺島さんに来ていただこうとダメ元で連絡したところ、なんと快く来てくださったのです。(2025/7/19)
寺島さんは、2019年春に地方紙の雄河北新報を退職され、その後はネットメディアTOHOKU360のメンバーとして記事を書いておられます。ネットメディアは数多くありますが、取材をもとに社会課題を扱うメディアはまだ限られています。
熱中丸森では、「震災関連の報道の場合、3000字とか5000字を使って書く必要があることが多い。その点ネットメディアは字数の制限が無いのがメリットである」という趣旨のコメントをされました。
一方で、紙の新聞を今でもとっているのは、一種の安心感からだと言われました。1日のニュースがパッケージになっている点が大きいと。私は寺島さんのこれらのコメントをおおいに共感しながら伺いました。
河北新報では、日頃のニュース取材のほか、「こころの伏流水」とか「オリザの環」といった、評判になった長期連載に携わってこられました。米作の問題を扱った後者は、私も読んでいました。(妻の父が、1週間ごとにまとめて河北を送ってくれていたのです。)
そもそもの“出会い”は、寺島さんの米国経験をもとにした『シビック・ジャーナリズムの挑戦--コミュニティとつながる米国の地方紙』(日本評論社、2005年)でした。その後、数年前に、坪田知己さんが企画された座談会で、私ははじめて寺島さんとお会いすることができました。
昨今、米国では地域のニュース砂漠化が深刻になっており、日本でも他人事とは言っていられない状況です。寺島さんには、全国各地の熱中小学校でぜひ講義をしていただきたいと願っています。
※下記リンクは、最近の寺島さんの記事です。仙台に新しい「街のにぎわい」生み出そう NHK仙台の番組制作者が東北大1年生と手を組み模索